Railsエンジニア
役員直下で遊び市場の課題を解決するサービスの開発に挑むRailsエンジニア
# 私たちは3つの事業を中心に余暇市場の課題解決に向き合っています。
【1】マーケットプレイス事業
休日の便利でお得な遊び予約サイト「アソビュー!」https://www.asoview.com
北海道から沖縄までのアウトドア、インドアの体験や、遊園地や水族館、日帰り温泉など、640種類、28,000プラン以上を掲載。予約・購入までできるサービスを提供しています。
アウトドアに特化した専門予約サイト「SOTOASOBI」https://sotoasobi.net/ や、「非日常」の体験を贈るギフトサービス「アソビュー!ギフト」 http://asoview.gift/ も運営しています。
【2】レジャー・観光・文化施設向け業務DXソリューション
大型施設のホームページで事前にチケットが購入できるように、アソビューが開発した直販ネット販売システムを導入し、外国人観光客や待ち時間軽減などに寄与しています。最近ではチケットを日時指定にすることで、施設内の3密対策に大きく貢献しています。
導入例)新宿御苑、世界遺産 平等院、レジャー施設(としまえん、サンシャイン水族館、海遊館など)、美術館・博物館(森美術館、奈良国立博物館など)、温浴施設(大江戸温泉、Spa Resort Hawaiiansなど)
全国のアウトドア事業者の予約・販売管理ツールとして事業者の事務作業の負担軽減や申込数増加に貢献しているツール「ウラカタ」の開発・推進も行っています。事業者にとってのペインを解消するために今後も機能改善・進化を遂げ全国の事業者の生産性向上に貢献していきます。
【3】ソリューション事業
中央省庁(観光庁・環境省等)を始め、各地の地方自治体と協業し、地域の課題に応じて体験商品の開発から情報発信まで支援を行い、地域の観光における課題解決に向き合っています。
具体的には、日本全国の地域を盛り上げるべく、体験商品開発やさらに売れる体験にする改善提案を行い、「アソビュー!」などで情報発信を行い、地域の魅力を「遊び」を通じて届けていきます。
最近は各自治体と協業し、地域クーポンの開発・販売を推進し、全国のおでかけ需要に応える取り組みに力をいれています。
/assets/images/17651622/original/59fa623d-fcde-4bd1-ad1b-bc668994b694?1713495514)





/assets/images/17651622/original/59fa623d-fcde-4bd1-ad1b-bc668994b694?1713495514)


/assets/images/17651622/original/59fa623d-fcde-4bd1-ad1b-bc668994b694?1713495514)

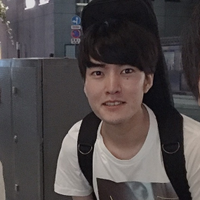


/assets/images/11012191/original/a878f62d-e8fe-47af-a779-bbb2bdde39e7?1667187638)
