自分のエッジはどうすれば見つかるのか――?「好きなことを仕事に」という風潮が強い現在、この問いは働く者すべてが抱えている問題でしょう。
この問いへの答えを求めて、今回はデジタルエージェンシーTAMのディレクターリーダー、小栗朋真さんに登場してもらいます。
TAM歴は20年以上を数え、顧客にも絶大な信頼を得ている小栗さんが、自分のエッジに気づくに至った経緯とはどのようなものだったのでしょうか?
若手社員の村上祐香さん、相澤英里奈さんとともに伺いました。
インターネット黎明期からの社員
―インターネット黎明期からパソコンに触れていたそうですね。
大学生だった1998~99年、ダイヤルアップ接続でインターネットにつないでいた時代に、アルバイトをしてパソコンを買いました。当時、イギリス・ケンブリッジ大学のある研究室のコーヒーポットをずっと映し続ける有名なサイトがあったんですが、それがたまらなく見たくて、買った記憶があります(笑)。
当時はまだブログという言葉すらない時代でしたが、ホームページの作り方、といった本を買ってきて、ソースコード直打ちでWebサイトを運用していました。名前は「クリイガ」(笑)。
エッセイを載せていたのですが、掲示板に毎日コメントがついたり、「全話プリントアウトしてファイリングしています」というファンの方ができたりと、当時としてはそれなりに人気だったんですよ。
大学卒業後、99年からTAMで働き始めました。当時はコピーライターに憧れていましたね。代表の爲廣から後に聞いたのですが、面接のときの印象は「なんて華のない男」だったらしいです(笑)。でも、その後に「クリイガ」を見て採用を決めたそうです。なんでもやってみるものですね。

―TAMに入ってからのお仕事は?
入社直後のTAMはグラフィック広告の仕事もやっていたのですが、翌2000年からデジタルに完全にシフトし、そのタイミングで憧れのコピーライターに抜擢されました。社内のライターは僕が初めてだったので、すべてが手探り状態。クライアントから直接「別のライターに代わってほしい」という厳しいお言葉をいただいたりもしました。
ライターはコピーを考えるだけではなく、方向性や企画をプランするところからスタートするので、徐々にプランナーを名乗るようになりました。
とにかく、当時はライター・プランナーは社内で僕一人だったので、ほぼすべてのディレクターの案件に同行してプランを担当する、という立場に。提案書を何本も平行して作るような、それなりに大変でストレスフルな仕事でした。
けれど、今思うとそうしてがむしゃらになんでも拒まずやってきたから、クリエイティブとテクニカル、それぞれにバランス良く引き出しを増やすことができたんだと感じます。
その流れで今度はチームリーダーになり、案件を作る仕事をするようになったのが12~13年前。今はメンバー20人の統括をしています。マネジメントをしたり、ディレクターのサポートをしたりするのがメインの仕事です。
僕のチームは特定の技術分野に絞るのではなくて、全体像をプランニングするというところをやっています。だから、10年を超えておつき合いしているようなクライアントもいくつもあるんですよ。そういった深い絆づくりが、売上の数字にも現れているのかもしれません。
お客さんの「戦友」になる
―小栗さん個人としてのエッジはなんですか?

今回の取材を受けるにあたって、めっちゃ悩んでたんですよ。僕自身のエッジってなんなのだろう? 先に言ったような、クリエイティブとテクニカルをバランスよく云々っていうのは、エッジじゃないよな……と(苦笑)。
ただ、絶対的に自信があるのは、クライアントと同じ土俵で、同じ向きを向いて案件に取り組む、懐に入り込む力です。
クライアントが困っていたら、業務範囲外であろうが責任の所在が先方であろうが、一緒に悩んで次のステップを考える。逆にこちらが困ったことがあればそれも打ち明け、試行錯誤して切り抜けていくところを一緒に体験していただく。
泥臭いですが、プロジェクトマネジメントにトラブルはつきものですから、それが必要なんです。
そのときにいちばん大切なのは、タフに明るく対処すること。暗くグジグジと考えていてはお互いに嫌になってしまいますからね。
僕のちょっとした自慢は、案件をともにしたクライアント担当者から「小栗さんは戦友です」とよく言われることです。
「こんなんできるわけないやん!」みたいな仕事が発生したときも、お客さんと一緒にクリアするゲームみたいに考えているところがあって。「なんでも面白がれる」というのが、僕のエッジなのかな、と思います。
同僚と自分のエッジについて話をしたときにも「人間力があることじゃない?」と言われて、「ああ、エッジって特定の技術分野じゃなくてもいいのか」と救われました。

―なんでも面白がりながらお仕事ができるようになったのは、最初からですか?
ライター/プランナー時代はとにかくドタバタ苦しみながら走り回っていましたから、そのときに生存本能的にそういう力を発掘したのかもしれませんね(笑)。
物事を面白がるには2つあると僕は思っていて、1つは「禅の境地」なんですね。物事をありのままに受け止める。「これはすごく大変な仕事で、でもオレはこれをやるんだ」と。逃げられへんし、受け止める、みたいな。
もう1つは、物事が「AだからB」となるときに、裏側にはこういう仕組みがあるんだ、と納得いくまで調べて、根本を理解するということです。
例えば、さっきのコーヒーポットの中継サイトにしても、一方ではコーヒーポットをひたすらぼーっと見つめる。ああ減ったなー、ああ増えたなーって(笑)。その一方では、カメラが捉えた映像が、パソコンでどんな文字列に置き換えられて、どんな経路でこっちのパソコンまで届いて、どんな仕組みでまた映像に戻るのか、みたいなことを徹底的に調べるんです。
2つは相反するような気もしますが、これを使い分けて楽しんでいます。
―そうして面白がることができた、だけど今まででいちばんしんどかったお仕事はなんですか?
これまででダントツしんどかったのは、10年ほど前、不要なものを譲り合うWebサービスとネイティブアプリを開発したときでした。
Facebookが流行し始めたころで、WebアプリとFacebookをゴリゴリに連携させたり、超短納期でスピード開発したりと、他の業務をすべて仲間に引き上げてもらってもまったく追いつけない状況。
何日か泊まり込みでヘトヘトになるまで仕事をして、 「今日ぐらいちょっと帰らしてもらおうか……」と、夜中に一度帰ったことがあるんですが、帰ったら妻が起きてたんです。
なにかなと思ったら、家の中にコウモリが入って飛び回ってたんです。それで子どもの虫取り網でコウモリをつかまえて(笑)。
だけど、コウモリがいてくれたことが本当に嬉しくて(笑)。明日会社に行ったら自慢しよう、って。しんどいことがあると、どっかで「しめしめ」と思っているところがあるんです。
―ハプニングを楽しんでいる。強いですね。

それが、ありのままを受け入れる「禅の境地」のほうの面白がり方ですね。
僕はプログラマー出身ではないのですが、この案件では詳細な仕様の作成もできるかぎり自分でやりました。これは、もう一方の「根本まで理解する」という面白がり方ですね。
ユーザーのステータスと品物の取引状況に不整合は起こらないか、ということを徹底的に検討したり、Facebookの仕様を調査したうえでWebアプリ/ネイティブアプリとスムーズに連携するためのフローやデータ設計を行ったり。
おかげで、テクニカル脳も鍛えられました。デバッグを管理していたGoogleスプレッドシートが容量制限を越えて(当時20万セルだったと思います)、プログラマーと一緒になぜかお祝いしましたね(笑)。
「エッジ」は面白がりながら待つ
―今、自分の好きなことで食べていける人が出てきているし、少なくともそういう環境とかツールとかコミュニティがあって、以前より個人の選択肢の幅もグッと広がりました。そんな中で「自分でまずエッジを決める」という風潮が前よりも強くなっているような気がしますが。

それを自分で決めることができたら、それはいちばんすばらしいことだと思いますけど、それってなにも、今後の人生を左右する最初で最後の決定事項じゃないんですよね。
「私はこの才能があるからこれで生きていく!」と決めるのではなくて、とりあえず1年は試してみるけど嫌やったらやめる、みたいな感じで気軽にやっていったらええんちゃうかな、と思います。
エッジは探さなくちゃいけないんですが、エッジ探しはつらいことじゃないし、どこかのタイミングで決断しなければいけないことでもない。結果として現れてくれるのを待っていればいいんですよ。「面白がりながら待つ」みたいな感覚かもしれません。
―エッジは見つけようと思って見つけられるものでもなかったり、すぐに見つけなければならないものでもない、と。
はい、僕の場合は2つの面白がり方で一生懸命やってきたら、知らない間にエッジができていて、そのことを他の人に気づかせてもらった感じです。そしたら、これまでは難しく考えすぎてたとか、心配しすぎてたとか、そういう気持ちになりました。
面白がれば、焦らない
―ここから村上さんと相澤さんにご登場いただきます。お二人はTAMのディレクターで、現在は小栗さんと相談しながら、自分のエッジを探しているそうですね。

村上 はい。以前は金融系の会社で営業をしていたんですが、自分ひとりで生きていける力を身につけたいと思って、Web業界に転職しました。今TAM入社3年目で、いろんなことをやらせてもらいながら、自分のエッジを探しているところです。
小栗さんの「人間力」の話が出ましたが、なにがあっても小栗さんならなんとかしてくれる……という勝手な安心感を持っていて(笑)、そういう意味ではいろんなことに挑戦できるいい環境だと思います。
相澤 私はTAMに入社する前、モノ作りの会社で黒豆の販売サイトを作ったりしていましたが、今はWeb制作以外のところでエッジを見つけようと、小栗さんとも相談しています。
小栗 でも、相澤さんはすでに見つけているじゃないですか? 彼女は「日本刀」が好きなんですよ。
相澤 普段の雑談の中では、小栗さんにも日本刀が好きなことを伝えていました。だけど、日本刀は会社の利益には直接つながらないと思っていたので、TAMで「エッジを見つけよう!」と言われたとき、それは候補として思い浮かんできませんでした。
でも、社内面談のときにエッジの話をしていたら、小栗さんが「日本刀やってみたら?」と話してくださって。
それで、それまで躊躇していた腰を上げて、自分で日本刀の展示情報を集めたサイトを作りました。展示がまとまっているサイトが世の中にまだないので、ネットの情報を集めたり、美術館に直接連絡取ったりしてコツコツ運用しています。
まだまだこれからですが、これを通じてなにか次のキャリアアップにつながるヒントが出てきてくれたらなあ、と頑張っています。
小栗 仕事への貢献ということだけで考えていたら、始まっていなかったんだろうな……と思います。
「自分のエッジはこれだ!」と決断する必要はないけれど、ふと思った好きなことはやるべきですし、それを応援する会社でありたいと思っています。なにもやっていなければ、振り返ってもなにも見つからないので。

そういう僕も「ロックバランシング」にハマってしまって、はじめは趣味でインスタに写真を上げていただけだったんですが、今はECサイトを立ち上げて、“積んで遊べるインテリア” として商品販売もしています。いずれTAMの事業ともつながらないかな……と考えています。
村上 TAMにはそういう活動をしている人がたくさんいるし、選択肢もいっぱいあるので、その中でエッジを見つけられたらいいな、と思っています。
エッジがあると、「ディレクター×〇〇」の「〇〇」が決められるのかな、と。相澤さんの場合は「ディレクター×日本刀」で一歩を踏み出すことができた。小栗さんも石のストアができたし。私はディレクターで、その「〇〇」を探しているところです。
小栗 普段の仕事をしていてはエッジが見つからない、一刻も早く他で探さなくては、と焦っている人も多いように感じます。
ですが、エッジ探しはなにもないところから探し出す重たい課題、普段の仕事は給料のためにやらなければならない課題、と分けて考えてしまうとつらいですね。
この2つは混ざっていると思います。そして、面白がって一生懸命働いていれば、いつか見つかる、誰かが教えてくれるもの。
今は選択肢もいっぱいあるし、エッジを探さなくてはならないというプレッシャーがすごくあると思います。「次、なにしたらいいの?」という悩みは誰にでもつきまといますが、そんな気持ちをどこかに持っていられるといいですね。
―小栗さん自身もそういうことで悩むことあるんですか?
小栗 めっちゃ悩んでますよ。楽しく悩んでます(笑)。

株式会社TAM 共創/戦略プランニングチームリーダー 小栗朋真
TAM歴20年、コピーライター/プランナー出身の右脳型プロデューサー。困難を乗り越えるプロジェクトマネジメント力でクライアントとの長期に渡るパートナーシップを築く。趣味は石花(ロックバランシング)とファミリー野宿。ボンゴも始めました。
[取材・編集] 岡徳之 [構成] 山本直子 [撮影] 藤山誠



/assets/images/5818/original/27855b33-34d8-4fc8-986d-891836dcb7fb.jpeg?1495011949)


/assets/images/5818/original/27855b33-34d8-4fc8-986d-891836dcb7fb.jpeg?1495011949)



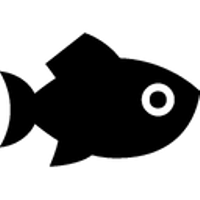
/assets/images/3478188/original/27855b33-34d8-4fc8-986d-891836dcb7fb.jpeg?1549953460)

