ふと気がつくと、人々の吐息が斜めに昇ることを確認できる季節になった。
しかし、今年は揃いも揃って口元に白い不織布を覆っている人が目立つ。
2020年を期に、強制的に世の中のデザイン変更が発表された。
それは、政治や権力といった恣意的な圧力ではなく、偶然にして必然的であるかのように、何者かが有無を言わさず、そして無断でキャンバスに描かれた絵を塗り替えてしまったのだった。
そして、表情に翳りすら感じる大きな空は、そのキャンバスをもう一度白紙に戻すまいと、いつも以上に多くの雪を落としていた。
〈0〉
「彼」は今から2年前、身分不相応なサイズの白いキャンバスを購入した。購入するやいなや、側にあったペンを使って絵を描き出した。彼は創造力に長けていたため未来の自分の考えを絵で表現することはお手のものだった。概念に囚われず、大きなキャンバスに自身の思考の全てを表現しようとする姿はまさに芸術家であり、エンターテイナーであった。喜びに満ちた雰囲気から連想できることは可能性以外の何物でもなかった。
そして、完成した絵画に、彼は『道』というタイトルをつけ、否応でも目に入る場所に展示をした。この絵を旗印に多くのオーディエンスが集まってきた。やがて、オーディエンスの中から彼の支援者になる者も現れ、支援者たちは彼を支えるためにそれぞれ活動を始めた。
とはいえ、崇高であるかと思えたその絵も、周囲からの意見は二分したのもまた事実だ。賛同の声もあれば、もちろん辛辣なものもある。元来、芸術に正解を求めるものではない。ゴッホのそれがそうであったように、作品というものは何年か遅れて賛同を得ることすらある。ただ絵を描いた時点では魅力が伝わりきらないことの方が多いものだ。
また、彼は『人』でありながら容姿がなかった。
だからこそ、必死に絵を描くということで自分自身の存在を証明しようとしていたのかもしれない。
そして、彼が成長し長生きするためには、良くも悪くも多くのお金が必要であるという事実があった。
〈1〉
この日、最後の商談を終えた宝井秀斗は商談先のオフィスから出るやいなやスプリングコートを纏った。もう4月になるというのに、寒かった季節に後ろ髪を引くかのごとく、少し肌寒い風を吹かせていた。
「またか・・・」ため息混じりに発せられた細く掠れた声は、風とともに消えていった。
新卒採用活動を支援するサービスの営業活動を行なっているが、ここのところ契約が取れていなかった。というも、世の中のデザイン変更の発表が話題になっていたが、それに伴い本格的な工事に取り掛かるとのことで、全国民に対して外出の自粛が命ぜられ、飲食店やテーマパークは軒並み休業となった。この通達は採用市場にも大きな不安を生み出し、先行き不明として買い控えをする企業が増え始めていた。特に新卒採用市場では、夏季のインターンシップの準備に動く企業が増え、例年であれば忙しくなりつつある時期であるのだ。それが今回の一件で、多数の企業が様子見を選択。また、契約目前の企業からは取消しの電話が鳴り始めていた。
さらに、外出自粛が促されると、お客様との接点を作るところから苦労をする。宝井の所属する会社では企業に電話をかけて自社のサービスを伝え、相手に興味を持ってもらうことができれば、商談の時間がもらえるというスタイルの営業だ。専ら電話越しにサービスの価値を伝える力は必要になるが、相手がいないことには価値を伝えるに及ばない。企業からの問い合わせを促進する仕組みを事前に構築しておくべきであったと嘆いたが、言っていても仕方がない。
採用を担当している旧友や知人へはSNSで営業を掛け、採用を担当していない友人や先輩には採用担当者を紹介してもらうようお願いをした。しかし、案の定の返答で項垂れるしかなかった。
契約が取れていないという事実と、先が読めない状況を考えると暗い気持ちが宝井を襲った。それと同時に向かい風がコートをはためかせた。身体の向きと駅の方向が反対であるということに気がつき、両手をポケットに突っ込んだ後、踵を返して足を送り出した。
〈2〉
各企業の商談進捗がノートパソコン一面に映し出されている。セールスフォースというシステムを導入して数ヶ月が経過したが、過去最低の商談進捗数となっていた。商談を9つに細分化して進捗管理を行っているが、一定のところから進んでいないケースも珍しくない。
「今月の見込み案件は?」という仲間からの質問に宝井はかぶりを振るしかなく、遣る瀬無さが立ち込めていた。Zoomを使ったオンライン会議も既に十数回を数えたが、この日の会議にはどういうわけか集中ができず、聞き耳を立てながら、近くにあった黒い表紙の書籍を手に取り読むわけでもなくペラペラとページをめくり続けていた。
「宝井さんからの決議案や相談事項はありますか?」
気がつくと、Zoomの画面の奥から北村賢が問いかけてきている。
「自分からは本日ありませんが、1点報告がございます。」
「お願いいたします。」
「今月、来月の進め方についてお伝えします。現状設計しているプロセスのコンバージョンレートですが、提案化率及び、受注率は度外視いたします。」
「ちょっと待った。それはどういうことか説明をしてください。」
今度は小川徹哉が尋ねてきたが、一瞬眉間にシワを寄せてたように見えた。小川の髪は綺麗に搔き上げられているものの、最近は専らコンタクトレンズよりも眼鏡を好んでいるため、確認がしづらかった。
「必ずくるであろうタイミングに向けて、今は現状の体制を整えるということです。」
このように返答した宝井は半ば緊張していた。ここまでの発言は捉えようによっては直近の売上を放棄することとも捉えられるためだ。しかし、宝井にはこれらの発言に至った裏付けが存在していた。
実はこの時、当初の想定とは違った結果が出ている点があった。アポイントの数である。4月は過去最高の進捗でアポイントが出てていると言う事実が存在していた。これは、メンバーそれぞれの努力に過ぎないのだが、瞬く間に広がったオンライン商談の常識化が後押しをしたことで、日本全国が営業の対象企業となったことが大きな要因だ。とりわけ、地方企業の採用に関する情報取得の意識は高く商談機会を得ることが多かった。
しかし、多くの企業が「採用活動が再開する時のための情報収集」といった名目のため、具体的な提案に至らない(提案に至らないと言うことは受注にも至らないということである)。つまり、画面越しに対面するだけでしかない。
だが、宝井自身はこの事実に着目をしていた。これまでのデータを見ると過去に一度でも対面をしている企業は、対面していない企業と比べても提案化率は15%ほど高かったのである。「今は企業がお金を払うタイミングではない」と想定した上で、然るべきタイミングに高いコンバージョンレートを生み出すために接点を作っておくことが、もしかすると今後生きてくるのではないかと密かに前向きに考えていたのであった。すぐさま、重要なKPI(重要業績評価指標)に企業対面数を設定し、チャンスがあれば確度が低くてもアポイントに繋げるように動いていた。手段の目的化とも考えられる策ではあるが、この瞬間に出来得ることを広げていた。
会議が終了すると宝井は考えに耽りながら、先ほど手に取っていた黒い表紙の書籍を手繰り寄せ、今度はじっくりと読み始めた。
〈3〉
GWも終了し、世間では例年通り5月病が話題となる時期に差し掛かった月曜日、宝井はとある企業とのキックオフミーティングに臨んでいた。twitterを開きスクロールをしていると必ずと言っていいほどその企業の従業員がつぶやいている。ListeNという企業である。
今回彼らにお世話になる案件は、問い合わせを促進しアポイント獲得をするためにBtoBマーケティングについてのノウハウを自分たちに蓄積することである。以前から、リードと呼ばれる日々の営業活動において見込みのお客様を獲得することに注力をしたかったのだが、勝手がわかっていなかった側面もあり、このタイミングでようやく着手をすることに決めたのであった。
「はじめまして。ListeNの低山です。」
年齢は宝井よりもいくつか下らしいが、非常に落ち着きのある男性だ。低山という苗字だけあり、声のトーンも低いなと宝井は心のなかでツイートした。
低山からの指導のもと、これまでになかったコンテンツの作成に取り掛かり始めた。まず着手したことは自社のナレッジをホワイトペーパーというスライド資料に纏めて、noteを使って拡散するというものである。時流はオンラインでの採用活動に対する正攻法を探しているタイミングであり、そのニーズに合わせてコンテンツの作成に取り掛かった。この時、自分たちは市場のニーズに対して向き合うことが出来ていたのだろうかと宝井は想像を張り巡らせた。確かに、ネガティブな状況が続いているとはいえ、最終的には市場が求めているものを発信しない限りは上手くいくことなど有り得ない。自分たちが劣勢状態に在りながらも、絶えず市場に耳を傾けながら持ち得ていることを様々な形に変容させ提供していく姿勢を見せる必要があることを再認識していた。
自分自身が蓄積した知識を含め、資料や文面に落とし込む作業は、取り掛かってみると想像以上にタフであったが、いきなり成果に結びつかなくとも、外部からの小さなリアクションを感じることが出来たため宝井の精神的な支えにもなっていた。
これら一連の活動によって、貸借対照表には記載されないものの、確かな資産を積み上げているという実感があった。
〈4〉
鏡を見ると一瞬他人が映っているかのように思えた。とはいえ、鏡に映し出されているのは宝井本人である。肌は荒れ、所々に吹き出物が散見された。睡眠不足が祟ってしまったのだろうと思っていたが、やはりそれ以上に結果がついてこないという事実に対して、焦りと不安、そして不甲斐なさが付き纏っていたのかもしれない。
そしてさらに、気がかりなことがあった。このタイミングで、主要メンバーの離職が相次いでしまっていたのだ。彼らは、自らの時間を投げ売ってでも企業に対してアポイントを取り付けるような精鋭達であるのだが、大きな変化のない組織において、少なからず不安を感じてしまっていたのだろう。そして、その不安を払拭しきれなかった自分を忌み嫌った。変化を作り出せないと言うことは、自分だけの悩みではなく組織の悩みにすり替わると言うことを大いに理解した。離職者が相次ぐと組織としてうまく機能しないことを意味する。振り出しに戻ってしまうことを覚悟するも、早急に考え、対処しなければいけないことが山積みで、何から着手するべきなのか、そしてどのような方向性で改善をしていくべきなのか、頭を抱えながら考えていた。
〈5〉
大阪メトロ御堂筋線本町駅から歩いて5分ほどのところに居酒屋『あすなろ』はあった。飲み屋が何軒か入っているビルの4階だ。エレベーターを降りるとそれなりの匂いを漂わせ、空腹を刺激すると同時にビールを矢継ぎ早に流し込むことを想像させた。
外出自粛が少し緩和されて暫くした6月の某日、定期的に会っている組織コンサルティングの事業を展開している社長との会食ということで宝井は少しばかり顔をこわばらせていた。というのも、この社長は、毎度的確且つ全うなアドバイスが多く改善点を浮き彫りにされる。そのため会が終わった後の宝井は毎度顔を俯かせながら帰路についていた。
先に店に到着をした宝井は、茶色い髪を肩まで伸ばした瓜実顔の女性スタッフに席を案内をされた。しばらくすると、褐色肌に短髪の大柄な男が店内に入ってきたことが確認できたため、宝井は徐に起立し遠くに向かって会釈をした。仕立ての良い紺色のストライプのスリーピースに、薄紫のシャツを第二ボタンまで外した出で立ちで、いつものバレンシアガのクラッチバッグを抱えている。今日のスーツの生地はロロ・ピアーナだろうかと宝井は想像した。
着席すると同時に淡路行宏は質問を寄越した。
「お疲れさん!今日はなんなん?」
「あ、はい。まあ、結構苦戦してましてね。」
「まあ、そうやわな。とりあえず、乾杯しよか。」
「淡路社長がお見えになったタイミングで濃いめのハイボールを注文しておきました。」
「おう、ありがとう!てか、こないだ言うてたクロケットアンドジョーンズの靴買ってん。ほら!」
この淡路という社長は自分のペースで話題を展開することが特徴である。天性的に主導権を握ることに長けていることが、普段の営業活動に活かされているていると宝井は睨みをきかせていた。先程の瓜実顔の女性からハイボールとビールのジョッキが運ばれてくると、間も無くクロケットアンドジョーンズの話は終息し、そそくさと乾杯に移行した。
「宝井くんさぁ、どんだけやってんの?」
「はい?何をですか?」
「いや、苦戦してんねんやろ?そんなん皆んなやし別にどうでもええから、組織に貢献するために何をどんだけやってるん?確かに俺の知り合いの採用やってるところも大変らしいし、売上上がってないっていうてるけど、言うててもしゃあないからな。」
宝井はその質問に対して考えを張り巡らせ、自分自身がどこまでやりきれているのか。ネガティブな市場環境とは言え「頑張っているつもり」でしかないのではないのか。そして、思っている以上にやり切らないと昨今の市場は絶対に応えてくれないと認識した。
「自分が頑張ろうが、会社にとってプラスになってないんやったら全くもって無意味やで。実際に自分がどんだけ会社に対して貢献できてると思う?特に君らのフェーズやったら結果が全てやわな。でも、結果だけが全てじゃないのも事実やで。外から会社に何かを持ち込んでるか?学びや思考を共有してるか?共有したことで自分だけじゃなくて他のメンバーの学びは増えたか?これがすぐに出てこやんかったら、いよいよ存在する意味無いで。」
淡路の口元から離れた空のジョッキが机に勢いよく落とされ「ドン」という大きな音を立てた。それと同時に沈黙が広がった。この沈黙から来る虚無感というものは、何歳になっても仲良くなれるものではないと宝井は思った。しかし、虚無感を感じるからこそ次の行動に思考を移すことができるのもまた事実である。
「俺はなぁ、会社のメンバー全員の年収を1,000万円にすることを目指してんねん。」
「何故ですか?」
「分かりやすいから。」
「社会人のステータスとして一定ラインでわかりやすいと言うことですか?」
「まあ、それもあるな。やっぱ、経営してる以上、他のメンバーにも自分ごとで会社のこと考えてほしいと思ってる。結果もそうやし、さっき言ったみたいに自分で圧倒的に考えて何かを会社にもたらしてくれるような存在になってくれると嬉しいよな。毎日の行動も、思考も会社の理念の理解も完璧やなって思ったら、金なんていくらでも出すねんけど、俺が1000万出すって判断しするやつは相当完璧なやつやろうな。そんな集団を作りたいし、何よりな、メンバーに還元する根拠がほしいねん。わかる?まあ、今20人おるからまだちょっと先やなって思ってんねんけどな(笑)」
出会ってからこれまでの淡路の性格、行動、発言を振り返ると、この真意は合点がいく。そして、多くの社長が同じ思いなのかもしれないと感じた。小さな組織であればあるほど、強いられるのは小なりの戦い方である。ランチェスター戦略のように、小さな市場に狙いを定めてニッチで首位を取りに行くということもそうであるが、何よりもまずは、一人ひとりの組織に対するインパクトを常に念頭におきながら、日々生産的な活動を続けなければいけない。一杯の水を持ち寄るとはよく言ったもので、どのように組織を強くしていくのか、どのようなアウトプットをしていくのか。これらを理解し会社を自分ごととして日々の活動に繋げていくことが、小なりの戦い方のスタートラインであろう。
最後に、淡路は宝井に対して、子を見るような視線を送りながら助言を渡した。
「どういう状況であろうが、インサイドセールスの部隊を時間かけてでも作っていった方ええわ。テレアポ部隊も良いねんけど、やっぱり精度変わるで。CAC(顧客獲得費用)もかなり抑えられると思う。」
ありがとうございますと口にすると同時に、虎視眈々と何かを狙っている雰囲気を纏いながら、着手すべきことを頭の中で整理をしていた。ジョッキに半分ほど残ったビールを一気に流し込んだ。口元から離した勢いを利用して、手に持つジョッキで「ドン」という大きな音を立て、次のドリンクを注文した。
〈6〉
60日ぶりに新規のお客様からの成約の知らせがあったので、宝井は肩をなでおろし安堵の表情とともに、周囲に聞こえるくらいの大きさでため息を漏らした。ようやく目に見える形で成果が現れた。それは確かに大きな金額ではないが、確かで大きな一歩である。そしてこれは外出自粛期間中に対面を目的として接触した企業からの成約であった。
さらに、コンテンツ作成によって獲得した見込みのお客様からも成約が生まれた。聞けば、ダウンロードした資料がよく纏まっていて分かりやすく、商談当日も自社で導入したことをイメージし易かったということであった。
蒔いた種が芽吹き始めた。
また、フィールドセールスのプロセスを見直しながら、仕組みに落としていく作業もひと段落した。そして、想定通りのプロセスで成約に至ると非常に爽快感を感じることができていた。曇り空からそっと顔を出す太陽が宝井の足元を照らしているかのようであった。
ただ、少数の中で、高い生産性を維持しながら決定的な違いを生み出すためには、足りない部分があった。やはりインサイドセールスである。先日、淡路からも助言があったが、未だに組み立てに着手ができていなかった。そこで、書籍やネットから記事を拝借することで知識を蓄えることに専念をした。さらに、実際にインサイドセールスの担当者やマネジャーに時間を頂きミーティングの機会を得ることに注力していった。その中で学んだ大きな気づきは「インサイドセールスの組織構築においては人材の採用及び、組織運営が絶対のミッション」であり「学習と成長のサイクルが早い傾向にある職種のため、未経験者の採用や登用に関しても積極的に行うべきである」ということであった。
これを、まずは学生インターンで立ち上げ、形を構築できれば面白そうだ。と宝井は想像を膨らませた。そしてこれから、まずは採用活動に取り掛かろうと動き出した。
〈7〉
11月で「彼」が誕生して2年が経過した。
そして、ふと気がつくと、人々の吐息が斜めに昇ることを確認できる季節になった。
しかし、今年は揃いも揃って口元に白い不織布を覆っている人が目立つ。
今年は強制的に世の中のデザイン変更が発表され、何者かが無断でキャンバスに描かれた絵を塗り替えてしまった一年であった。
そして、表情に翳りすら感じる大きな空は、そのキャンバスをもう一度白紙に戻すまいと数年で最強の寒気を引き起こし、いつも以上に多くの雪を落としていた。
〈8〉
真っ白な一面の雪景色の中にそっと佇んでいた。
何かに手繰り寄せられるかのように足を送り出した。
5分ほど歩いただろうか。
後方から、呼ぶ声がしたので後ろを振り返ってみた。
その声は気のせいであったが、振り返り見るとそこには精密に計算されたかのような等間隔で左右の足跡が並んでいた。
あまりの美しさに目を剥き、絵画の如く『道』というタイトルをつけてみた。
そして、正面を向き直した。
目の前に広がっている一面の巨大な白いキャンバスに、確り踏み締めながら、この絵画の続きを描いて行こうと思った。
ただ、出来上がった作品は数年遅れて賛同を得るのかもしれない。
今度は「彼」だけではなく、宝井も絵画活動に加わることを決心した。
ふと、歩道沿いに目をやると、梢に咲く雪の花がこちらを見て微笑んでいた。


/assets/images/3695719/original/2b4e68e6-539f-478b-8c53-13c9a1581b84?1560917638)


/assets/images/3695719/original/2b4e68e6-539f-478b-8c53-13c9a1581b84?1560917638)
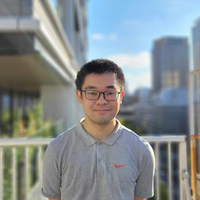


/assets/images/5887079/original/a3eb6b55-9a04-47f0-875c-8180e8c5e57d?1607296978)

