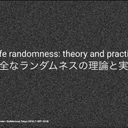Business social network with 4M professionals
Kenji Rikitake
力武健次技術士事務所 / 所長
自分以外は全員無視して進め
1965年生まれ。プロフェッショナルインターネットエンジニア。10歳の頃、アメリカ合衆国コロラド州ボールダーに在住。その時以来英語とコンピュータとの付き合いが続いている。 1990年にDECのVAX/VMS OSの開発者としてソフトウェアエンジニアの仕事を始め、1992年よりインターネットの運用技術の研究開発に携わる。2008年よりErlang/OTPのコミュニティ活動を始める。
Ambition
これから IT が 医学・農業・環境などの実社会に貢献していく中で、情報技術の専門家として社会基盤を支えていきたい。
- ラジオ受信ソフトウェアairspy-fmradionを開発
SoftFMとNGSoftFMというソフトウェアをベースにしたものを大幅に拡張し、FM放送だけでなくAMやSSBの受信も可能にした、オープンソースのラジオ受信ソフトウェアを開発しました。 2019年でもっとも力を使った研究作業だったと思います。
Bashoジャパン株式会社8 months
シニアソフトウェアエンジニア
Erlang で記述された分散キー・バリュー・ストアである Riak について、特にセキュリティがより良く担保されることを目指す。
京都大学3 years
国立大学法人 京都大学 情報環境機構 IT企画室 教授
京都大学の全学キャンパスネットワークと情報システムを含む情報基盤の インターネット/情報/コンピュータ・セキュリティについて 戦略的立案と技術コンサルティングを行う。
学術情報メディアセンター 連携研究部門 情報セキュリティ分野 教授
大規模並行並列分散コンピューティング環境におけるインターネット・セキュリティ技術の研究。
独立行政法人情報通信研究機構(NICT)5 years
情報通信セキュリティ研究センター インシデント対策グループ(旧セキュリティ高度化グループ)専攻研究員
インターネットのセキュリティに関わる技術的課題の解決に取り組む。侵入検知の可視化・分析システム NICTER の概念設計を行う。
- C以外の言語を調べる中で Erlang に出会う
DNS のサーバーというのはC言語で書かれているのですが、ヘッダーだけで1000行あるというものでエンジニアとしてこれを続けていては成長が難しいと思い、他の言語を色々調べる。 その中で Erlang に出会った。Erlang は不変性・並行処理などを備え、分散システムを構築するための先進性がある言語・処理系であると考え、これを使おうと思った。
-
大阪大学大学院2 years
情報科学研究科 マルチメディア工学専攻 博士後期課程
KDDI 研究所の上司の薦めもあり、大阪大学との共同研究でドクターを取ることを志す。
株式会社KDDI研究所5 years
セキュリティグループ 主任研究員
自分自身のDNSとリモートワークへのこだわりから、そういった実践の中で見える技術的な課題を解決するために、DNS、IDS、リモートワークの3本柱で研究を行う。
情報技術開発株式会社9 years
京都ネットワーク技術研究所 主任研究員・所長代理
まだ誰も先が予測できなかったインターネットについて、つないでいくこと、使っていくことそのものを、研究と実業の両方としてやっていく。
- 企業内ネットワーク運用と WIDE 京都 NOCの運用を支援
企業内ネットワーク運用では東京、大阪、福岡、名古屋オフィスをどうつなぐか、IP アドレスをどう分けるかなどを考える。NOC では特定の組織と広域ネットワークとつなぐ運用を行う。
-
日本ディジタルイクイップメント株式会社3 years
研究開発センター 国際システム開発方式部 ソフトウェアエンジニア
オペレーティング・システム VMS を改善すること。もともと DEC が設計を行った VMS のユーザーだったので思い入れがありました。
東京大学6 years
大学院 工学系研究科 情報工学専攻 修士課程
HHKB で有名な和田英一先生の研究室で学ぶ。当時、ZIP など複数の無損失データ圧縮アルゴリズムが出てきた時代であったため、修士論文での研究ではそれらのサーベイを行った。
工学部 計数工学科 計測工学コース
温度、気圧、湿度など、さまざまなものから情報を取得することについて学ぶ。コンピュータ技術に限らず、電子工学など物理的な領域も取り扱った。