FICC代表取締役の森啓子さんは、幼い頃から海外生活の経験も多く、リベラルアーツを大切にする環境で育ってきたといいます。なぜリベラルアーツの考え方が経営に生かされるべきなのか?といったビジネスの話だけでなく、人と関わる時に心がけていることなど生きる上で大事にしている森さんの思想の深淵に触れてみたいと、アートを中心とするエディター・ライターの中村志保さんが聞き手となり、対談を行いました。前後編に分けてお届けします。
多様な視点を持つ力

中村志保(なかむら・しほ)1982年ニューヨーク生まれ。慶應義塾大学文学部美学美術史学専攻卒業。ロンドン大学ゴールドスミス校にてファインアートを学び、同校メディア学部イメージ&コミュニケーション専攻修士課程修了後、保険会社に勤務しながら作品制作。その後、『TRANSIT』編集部、『美術手帖』編集部、『ARTnews JAPAN』エディトリアルディレクターを経て、現在はフリーのエディター・ライター。
中村:今日はよろしくお願いします。今回は、森さんがどうしてリベラルアーツという環境を大切に考えているのか、アートを学んだ学生時代やバックグラウンドも含めて掘り下げながらざっくばらんにお話を伺えたらと思い、対談の機会をいただきました。早速ですが、リベラルアーツについてお聞きしていきたいと思います。
森:リベラルアーツの根源には人を自由にする学問だという考えがあって、何か特定の思考やものにとらわれず、お互いの視点(パースペクティブ)を得ることで自由に生きていける、というのがリベラルアーツの本質だと思うんです。
中村:「自由」とは何もルールがないということではありませんから、一つの見方にとらわれないというのは、すごく本質的ですね。
森:昨日は社内で、社員が企画してくれた「哲学対話」(参加者が輪になって問いを出し合い、一緒に考えを深めていく対話の在り方)をしている時に、自分とは異なる価値観で生きている人の話に、「なるほど、そういう考え方もあるんだな」と改めて感じたことがあって。
私の場合は、頑張り続けるのが癖のようになってしまっていて、子どもの頃からブレイクしたり手を緩めたりということをしてこなかったんですよね。息を抜くことに勇気が必要で……。

森啓子(もり・けいこ)米マウント・ホリヨーク大学 BA(文学士)、米マサチューセッツ芸術大学大学院 MFA(美術学修士)課程修了。米国デザイン・広告会社で勤務後、2005年にFICCに入社。2019年に代表取締役に就任。ブランドマーケティングを専門とするFICC。経営のコアに「リベラルアーツ」を掲げ、人の想いや学びを通じて社会への価値を創造し続けるイノベーティブ組織から、ブランドと人の想いが大切にされ続ける社会を目指す。
中村:哲学対話とは、どんなことを話題にするんですか?
森:昨日の参加者は10人ほどだったのですが、「不安」について話し合いました。「不安とは○○である」と言葉にしていくのですが、「不安ってどういう時にあるんだっけ?」と問いで返しながら進めていくんです。
中村:他の人の意見を否定せずに聞き合う、と。
森:そうですね。その中で、不安を感じる時や大変な時に誰かに伝えるか?という話になって、私は今まで人にあまり伝えてこなかったなと改めて思いました。両親や先生からもよく言われていたのですが、子どもの頃から手がかかる状況になったことがなかった、と。でも、それこそが自分の弱みだなと思います。
でも最近は、自分がつらいと思っていることを伝えることも大事だなと思うようになってきて。そのほうがむしろ周りと一緒に頑張れる関係になれることを、43歳になってようやくわかった感じです(笑)。
中村:森さん自身に変化が起きているのですね。
森:頑張りすぎなくていいんだと少し思えるようになってきました。中村さんは、つらい精神状態の時は人に伝えますか?
中村:「無理です、助けて!」と人に伝えることはあまりないかもしれません。小さな会社でしたが、過去に勤めていた時は他の人にあまり頼らなかったかも。これをお願いしたら嫌かな、と気を遣ってしまって指示を出すのがヘタで。でもそうすると新しく入ってくる人が伸びないですよね。だから、今の自分にはフリーランスという働き方がとても合っていると思います。
森:気を遣ってしまうの、すごくわかります。だから最近は「私、大変だと伝えるのがヘタなんだ」と意識的に言うようにしています。
中村:言葉で伝えるのは大事ですよね。私はライターという職業柄、インタビューする機会が多いので、いろんな分野の研究者の話を聞くこともあれば、小説家や俳優、ミュージシャン、画家、夜のお仕事をしている人、主婦、ホームレスの人に話を聞くこともあります。そうやっていろいろな方に話を聞くことで、私自身が保たれて、生きやすくさせてくれているような感覚があります。

森:多様な人の人生観や、一人ひとりの「生きる」に触れるということですね。
中村:特定の業界内で当たり前とされていることの中に浸かっていると、どうしても視野が狭まってしまう感覚があって。いろいろな職業の人や、時にはプロフェッショナルではない人の思いや考えを聞くようにしています。
でもすごく面白いのが、いろいろな経験をして切磋してきた人が共通して、「全てはつまらないし、全ては面白い」とか「今も昔も子どもみたいに楽しんでいるだけ」と、すごく共通する言葉を持っていること。ある種の悟りの境地に到達するとそこに行き着くのだろうなと感じます。森さんも、いろいろな人に会ってお話しすることが多いですよね。
森:私も人の見ている世界に触れ続けるのがとても好き。自分が見ている世界の見え方は人それぞれ違いますよね。その人が何を見ているのかなと感じるのが好きで、物事に対する感じ方を知るというか、触れるというか。
ただ、これは好き……ということだけでなく、先程お話した哲学対話でもテーマになった「不安」もあるのだと思います。「○○診断」のように、人が見る情景や世界を、なにかに結論づけようとすることに対して、人よりも「不安」を感じることに気づきました。その情景を決めつけた瞬間に、人の可能性が終わってしまう。ただ、同時に思うのは、定義されることへの安心感はグラデーションのように人それぞれなので、一緒に共存する上での「最大余白、最小ルール」というのはなんだろう?と、最近ずっと考えています。
相手の世界観を想像すること
中村:森さんは幼い頃から海外に行かれていて、早い段階で「自分が見ている世界の見え方は人それぞれ違う」と感じるようになったのではないかと思います。言語も外見も違う集団の中にポンと放り込まれると、自分の力ではどうにもならないことがあることに嫌でも気づかされますよね。

森:言語がわからない環境に入った経験は大きいですね。そこにいると、相手の目や口、ジェスチャーを見て、相手が何を伝えようとしているかすごく考えることになる。言葉ではなく「感じる」ということに鋭敏になるのかなと思います。
中村:大なり小なりマイノリティの立場になった経験は多くの人にあると思いますが、すごく大事なことだと思います。
森:何かインシデントが起きるとか環境が変わるとか、そういう変化がないと、マジョリティ、マイノリティの視点を変えていくのは簡単ではないですよね。ただその中で、どう視点を得ていくのか。リベラルアーツや哲学対話で話していた、パースペクティブを互いに得ることにもつながるお話だと思います。
中村:そのようにもう一歩踏み込んで人を理解しようとしたり自分のことを伝えたりする時に、言語化はすごく大事なことだと思います。ただ、その伝え方や話し方によっては言葉そのものとは異なる受け取られ方をしてしまうこともあります。森さんは多くの人の前で講義やプレゼンをすることが多いと思うのですが、言葉で伝える時の工夫や意識していることはありますか?
森:言葉の選び方を重視するというよりも、自分が伝えたい世界観をどのように共有し合えるかを大事にしています。同じ空間にいる場合は、自分が大切にしたい世界の温度感が相手に伝わる空気を一緒に作れているか。プレゼンや講演でスライドを見せる時には、言葉ももちろんですがビジュアルにもこだわります。
中村:想像が膨らむような、感性に訴えかけるビジュアルですね。
森:そう、映像を作る感覚に近いです。使う言葉も自分が伝えたい世界観の「情景」になっているかを考えますね。自分が見ている情景のビジュアルを入れていくイメージです。話していることは会社のことでも、背景にはメタファーとして海の写真や、水族館のガラスの前にいる子どもの写真が映っていたりします。
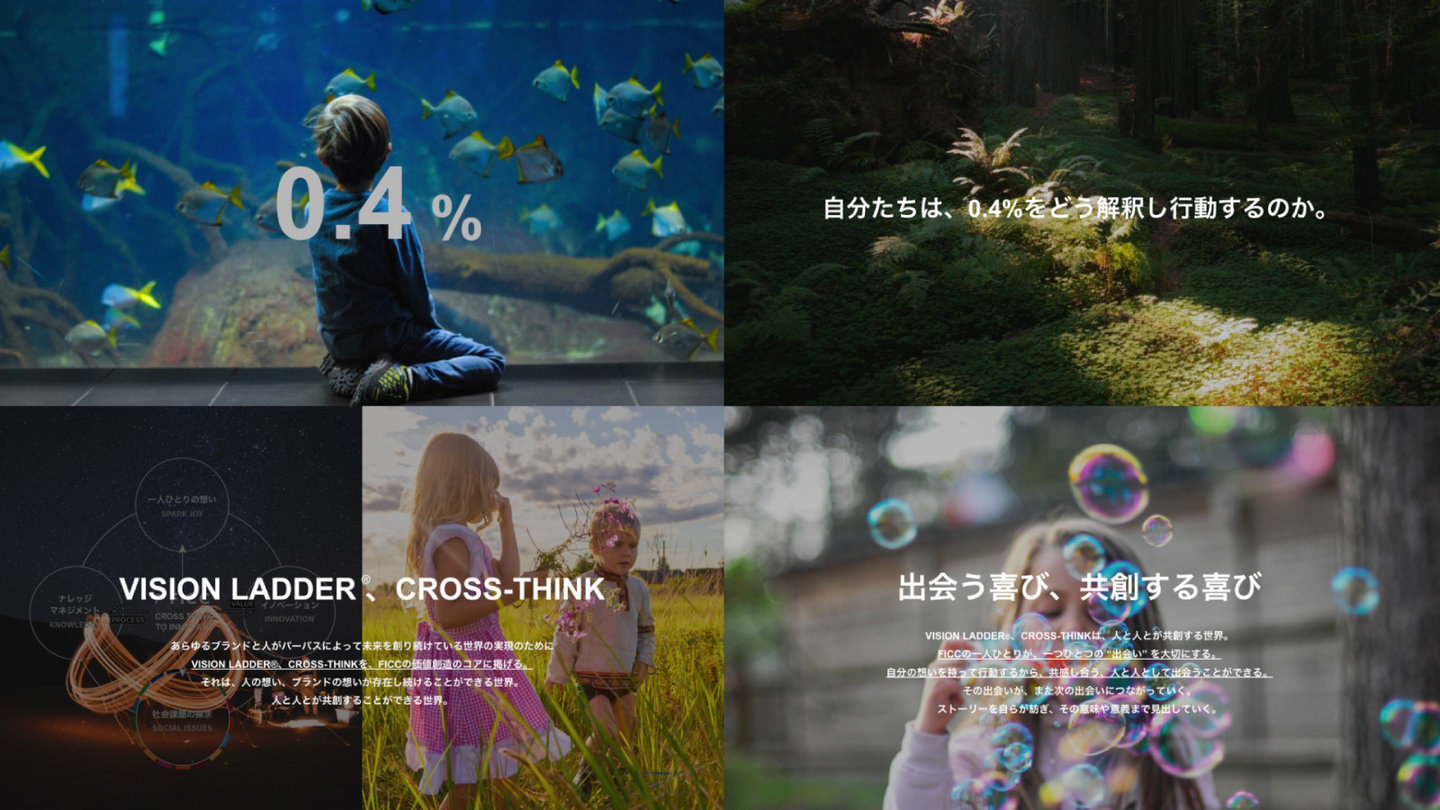
2023年4月の期首挨拶で、森が使用したスライド。詳しい内容は『変化しないものは淘汰される?0.4%の世界を変えていきたい』よりご覧いただけます
問いと問いがぶつかり合う場
中村:以前、ロンドンの副市長が「文化とダイバーシティ」をテーマに登壇するイベントがあったのですが、彼女のプレゼン資料に驚きました。言葉では統計を交えて論理的なことを話しているのですが、スライドには抽象画のようなビジュアルが投影されていることも多くて。

森:まだないものを相手に伝える時、未来へと向かっていこうという時には、説得力ではなく、想像力が大切になりますよね。想像力を掻き立てるストーリーテリングは、経営でも大切にしています。
中村:コミュニケーション手段として、ですよね。森さんがそのように考えるようになったきっかけは?
森:高校生の時にオーストラリアに留学した時に、スピーチを練習し続けるという経験をしました。“Palm Cards”と言って、要はカンペなんですけど、手のひらに収まるサイズにしたメモ書きを自分で切って作って持つんです。立って話しながら、さっと手の中を見るくらいで、A4サイズの紙に書かれた原稿を読み上げるようなことはしません。私も部屋の全身鏡の前で自分の姿を写しながら千本ノックのように練習をしました。
中村:堂々とわかりやすくお話しされる姿の裏には、訓練という努力があるものですね……。
森:抑揚をどうつけるのか、ジャスチャーをどうするか、見せるビジュアルは何にするか……と、相手のことを考えながら話すことを学んだと思います。あと、大学時代にアートを専攻していたので、自分が信じる情景を作品として創造していくことも、その情景に出会ってもらう体験も、今の経営の姿につながるものだと思います。

中村:そのようなプレゼンやディスカッションの機会を増やすことに、今は力を入れ始めている日本の学校も増えてきていると思うのですが、十数年前まではほぼなかったですよね。
森:ええ、本当に。しかも、海外に行くと自分の思いを語らないといけないので、オープンクエスチョンを渡されて「はい、どうぞ」という感じ。型がないんですよね。大学でアートを学んでいた時も、作品を創るだけではなく毎日クリティーク(批評)をやるわけです。人が沢山いる前で自分の作品を見せながら自分の情景や哲学を伝え、同時に他者の異なる視点も投げかけられ、対話や議論が続いていく。
中村:私もロンドンでファインアートを学んだのですが、批評・批判に重きを置いている大学で、自信喪失した経験があります(笑)。
最近、ひろゆきさんの「それってあなたの感想ですよね」というフレーズが流行りましたけど、大学では本当にそれに近いことをバシバシ言われました。何十人という生徒と先生に囲まれて、自分の作品を見せるだけでも怖いのに、「私はこう考えて、こう表現しようとしたんだ」と説明すると、「そう考えることになった文脈は?」と突っ込まれるんですね。それに答えられないと、「それでは感想に過ぎないよね」ということになってしまう。
森:私も号泣しながら帰ったこともあります(笑)。でも決して否定されているわけではないんですよね。これは世界と世界のぶつかりだ!と、奮い立たせていました。

中村:自分の思いを発するということは、それくらいの責任がともなうものなんだと知ることになりました。
ディスカッションの場でも、「その考えはどこから引用してきたの?」と、本当によく質問されました。一見自由なものに見えるアートというものも学問なんだな、と納得しましたね。
森:貴重な体験ですね。私が学んだ大学はリベラルアーツ環境だったので、「その考えはどこから引用してきたの?」と問われたことはありませんでした。その問いを起点とした世界を表現し、問いと問いとがぶつかり合うような場。いろんな分野を融合して自分の問いを立てる、という感じでした。
一人ひとりの「情景」が大切にされることこそ、リベラルアーツ
中村:「リベラルアーツ」という言葉は近年よく耳にするようになりましたが、「一般教養」と訳されることも多いです。でも、日本の大学の一般教養とはだいぶ違うと思うのですが。
森:私はリベラルアーツとは何かということを学んだのではなく、リベラルアーツが大切にされている環境で育ってきたと考えていただければと思いますが、そこで自分が享受していたものこそがリベラルアーツの大事な哲学だと思っていて。決して一般教養ではないんですよね。
中村:受け身の座学で獲得できるものではないですよね。
森:何事にも興味を持つとか、自分の世界だけが全てではないとか、先ほども話に出ましたが、一つの問いに対してひたすら皆で対話し続けるとか。例えば、まだ解決されていない数列のことを延々と皆で話したりするのですが、でも、答えが出るわけではありません。
それでも、お互いにどう考えるのかに向き合い続けること。相手の話を聞いて新しい考えに出会ったり、とにかく一緒に視点を共有しながら考えぬいていくような時間でした。自分が見る世界と、相手が見る世界に出会い続けるプロセスとか、環境そのものが重要なんですよね。私は、それこそがリベラルアーツだと思っています。

中村:森さんは、アートを学ぶ一方で数学も専攻されていたのですよね。
森:リベラルアーツの大学って、専門性のある学部を受けるという概念がないんです。大学に入学して、2年生の終わり頃に専攻と副専攻、またはダブル専攻にするかを決めるのですが、それまでは本当にいろんなことをやる。日本だとそれだけがピックアップされて「一般教養」ということになっているのかもしれないですね。私は専攻がアートで副専攻が数学でした。だから、自然と融合していくんですよね。
中村:日本の美術大学は一般的な大学と切り離されすぎているように感じます。アートってなんだか特別な分野に考えられがちですが、やはり学生の時期から同じ学内で、数学、物理、文学、心理学……と、さまざまな分野の学生と交流しながら作品を作るべきだと思うし、そうすることで異分野を学ぶ人たちもアートをもっと身近に感じることができると思います。

森:私も数学とアートを融合した作品を作っていたのですが、展示会に数学の教授が来てくださって、私の作品を通じて対話することもありました。人が見る世界や創造する世界に、どう反応したり、それが対話となって広がっていくのかというのがリベラルアーツの環境であったと思います。
中村:そのような環境は日本ではなかなか見ないですね。美大の受験ではかなりデッサンをはじめとする技術に力が置かれていて、「今日は木を描いてみましょう」とか「虫を描いてみましょう」という、ある意味では小学校の美術教育からあまり変わっていない部分が大きいような気がして。受験の時点でもう少し異なる評価軸があってもいいのではないかと思います。
森:アメリカでアートを専攻していた時も、何年もほぼ毎日、裸の人物をひたすらデッサンするんですね。それはデッサンのハウを学んでいるのではなく、自分と向き合い続けるプラクティス(習慣)だったと思います。例えば、自分はものすごく痩せている人を描くことが好きだったのですが、それは骨の複雑な影と光が美しいと思ったから。そんなことを感じたり考えたりするんですよね。
中村:物や人を観察して描くことは、どこか自分を観察することにもつながりますね。でも一方でやはりアートを仕事にしていくとなると、作ったものを人に言葉で伝えることがどうしても必要になる場面が出てくる。もちろん自由に見てもらうのも大事ですが、ただ「わあ、いいね」で止まってしまうのではなく、作家も鑑賞者ももう一段階深いところを想像したり、読み取ったりできることが必要なのかなと。
森:一つの評価基準で「この人はうまい」という選び方をしてしまうことが多いですからね。一人ひとりの想いや考えを見ていくと、可能性はストレッチすると思う。それが教育で大事な体験だと思います。
中村:これはアートに限った話ではないですよね。社会に出るといろんなことを学んできた人たちと交差するので、大学の時からそういうことがもっと起きるといいのではと思います。
絵を描いている人同士で話していれば、技術面にしても言わずに理解できるものがあると思うんですが、それこそ数学を学んでいる人に見てもらって、その人の意見をどう捉えるのか、と。やっぱり分野を超えた交流が大事だと強く思います。
森:そこからまた可能性が広がりますよね。あとは、主体がどこにあるのかという問題でもあると思います。評価についても、教育する側が主体なのか、それとも、そこにいる一人ひとりが主体なのか。どう捉えているかで教育のあり方は大きく変わる。「小学校が、はい、終わりました。では次は中学です」と、社会が決めた仕組みや枠組みで世界や時間軸を見るのではなく、本当は一人ひとりを軸に世界にどう問いを立てて学びに出会っていくのかというような環境が大切にされれば、豊かな社会になっていくはず。

中村:一般的な受験の制度も改善する必要があると思っています。普通は高校3年生までに受験する学部を決めないとならないですが、例えばその前に1年間でも、ボランティアや、自由に何か自分で考えたり経験したりする時間があって、それを評価してもらえる余地があったらいいなと。さらに、大学に入っても3年生の時点で就活が始まりますよね。
最近はキャリア採用も増えていますが、新卒採用が一番優秀で有利という考え方があまり変わっていないように感じます。いい意味で「遊ぶ」時間が少ない。本当は、日本一周の旅をするとか、海外に行ってみるとか、その中で見てきたものを働くことに生かしてもらいながら育っていくような企業の在り方だったら素敵だなと思います。
後編では、ぜひそのあたりを。森さんの思想がFICCでどのように生かされているのか、もう少し具体的にお聞きしていきたいです。
(後編へ続く)
/assets/images/1827349/original/ba183d40-328f-4d0d-b610-99b6bf390a5e?1506933699)


/assets/images/1827349/original/ba183d40-328f-4d0d-b610-99b6bf390a5e?1506933699)


/assets/images/1827349/original/ba183d40-328f-4d0d-b610-99b6bf390a5e?1506933699)


/assets/images/1827349/original/ba183d40-328f-4d0d-b610-99b6bf390a5e?1506933699)
