「Here we grow(成長する、親子とともに)」という新たなコンセプトのもと、親子の距離を近づける製品を発信する北欧・ノルウェー発のブランド、STOKKE(ストッケ)。一方、FICCのメディア・プロモーション事業では、一人ひとりのメンバーが社会課題に取り組むブランドに対して、真摯に向き合いながら支援を行っています。STOKKEでマーケティングマネージャーを務める福岡久美子さんと、デジタルマーケティングマネージャーの後藤悠子さん、FICCからはメディア・プロモーション事業部 京都の事業部長である村松勇輝と、プロデューサーの角屋桃子が参加し、子育てから家族の在り方、働き方、プロジェクトへの想いまで、熱く語り合いました。
コロナ禍で刷新されたSTOKKEのコンセプト

福岡久美子(ふくおか・くみこ) 株式会社ストッケ マーケティング部 マーケティングマネージャー
──まず初めに、STOKKEの特徴について教えてください。
福岡久美子さん(以下、福岡):STOKKEのベストセラー「トリップ トラップ」が誕生してから50年が経ちました。ブランド自体は1932年創業なので、今年でちょうど90周年ですね。そして、STOKKEが掲げる「Here we grow(ヒア・ウィー・グロウ)」というステートメントは、昨年11月に生まれ変わったんです。日本語では「成長する、親子とともに」という言葉で表しています。
実は、ブランドのステートメントを変更すると聞いた時はすごく衝撃を受けました。でも、意外とさらりと改めてしまうのは、すごいことだな、と(笑)。なぜ変えたのかというと、社会情勢の大きな変化にあります。新型コロナ禍になって2年ほどが経とうとするなか、人々の生活はコロナ前とはガラッと変わったことや、人種差別やジェンダーに対する考え方なども今までとは異なってきましたよね。
そのように社会の変化に合わせてブランドも変わっていかなくてはならない、とステートメントを刷新した経緯があります。もともとの「Designed to be Closer(親子がもっと近くなるかたち)」という製品のコンセプトはそのままに、社会全体で親子をサポートできる世界を目指して企業としても成長していきたい。そんな考えのもとに動いています。

2021年、東京・代官山にオープンしたショールーム兼オフィス「STOKKE HOME DAIKANYAMA(ストッケ ホーム 代官山)」にて取材を行いました
──親と子どもを取り巻く環境が変化しているなか、ブランドとして取り組むべき課題としてどんなことがあると考えたのでしょうか。
福岡:近年、子育ての仕方はとても変化していますよね。たとえば、今までは、出産したら里帰りをして自分の母親に子育てをサポートしてもらったり、出産前には両親学級が開かれて、出産にまつわるさまざまな知識や、授乳の仕方、赤ちゃんのおむつの替え方、沐浴の方法などいろいろ教えてもらったりしていましたよね。でも、コロナ禍で一切それがなくなってしまった。立ち会い出産もできないのでお母さんは病院で一人で出産して、その後の子育てもワンオペという家庭もいまだに多い。誰にも相談できず、孤独感を持つお母さんは多いと感じています。
STOKKEのノルウェー本社でも、社会に変化が起きているなかでもっと家族を支えるブランドになっていきたい、と感じていました。製品だけにフォーカスするのではなく、社会に貢献できるようなブランドになることを目指し、「Here we grow」というコンセプトに繋がっていきました。
STOKKEとFICCの出会いーー互いに共感し合う対話
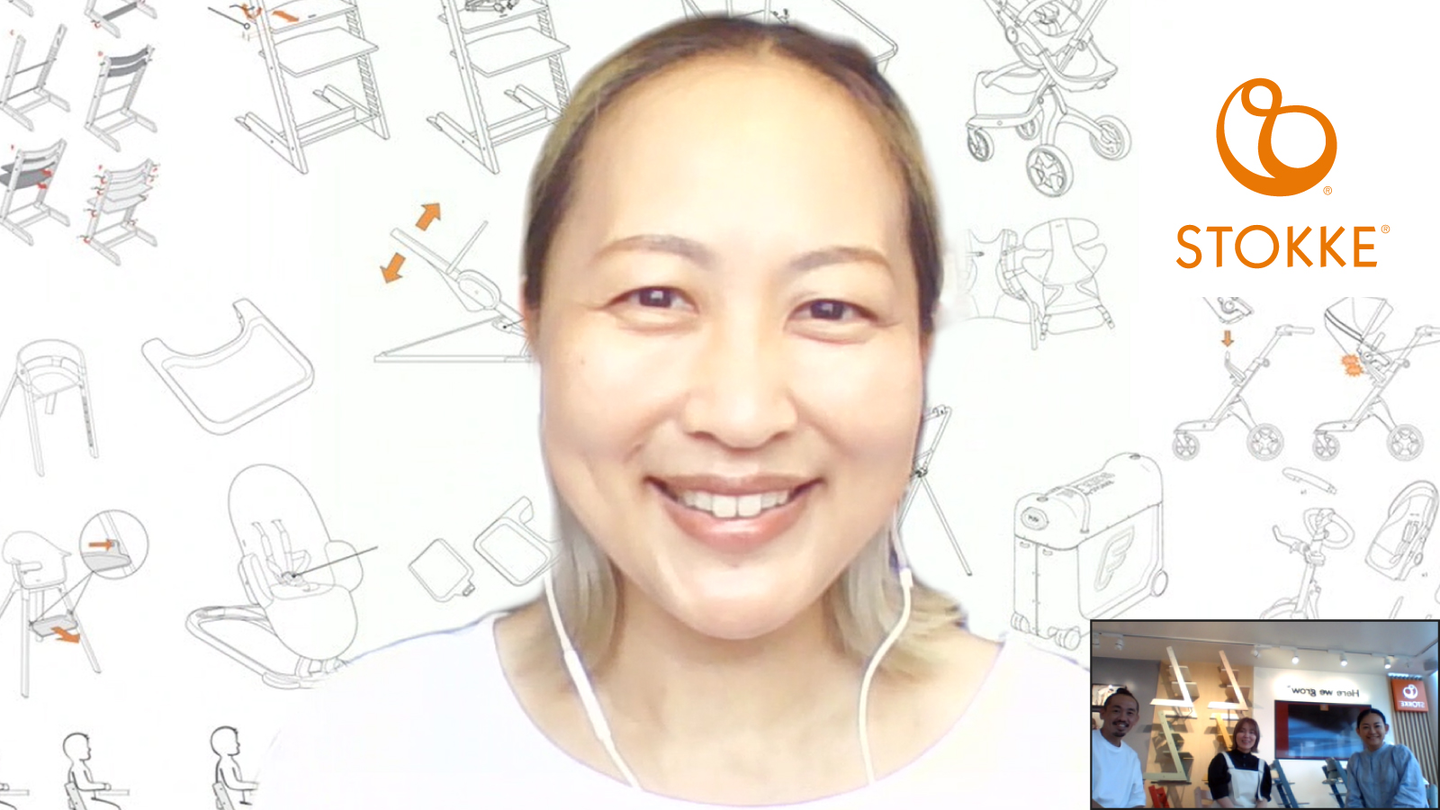
後藤悠子(ごとう・ゆうこ) 株式会社ストッケ マーケティング部 PR / デジタルマーケティングマネージャー。今回、オンラインにて参加いただきました
──FICCと協働して、各分野のプロフェッショナルを講師に迎え、産前産後の家庭が必要とする情報や知識などを発信したプロジェクト「ストッケアカデミー」へと繋がっていくのですね。
後藤悠子さん(以下、後藤):プレママ、プレパパの不安な気持ちを支えたいという想いから、FICCさんにお声がけさせてもらって、2021年に開催したオンラインセミナーですね。
福岡:コロナ禍ではほぼ外出できない状態でしたよね。特に妊婦さんや、赤ちゃんが生まれたばかりの家庭では、専門家から出産に関する知識を教えてもらえる機会が少なくなってしまったことが、深刻な問題になっていたと思います。そこで、妊娠期間中に学んでおきたい知恵や知識を、助産師、理学療法士、乳幼児睡眠コンサルタントなどの先生に教えてもらうオンラインセミナーを開いたんです。週に一度、計4回をセットにしたセミナーで、半年間行いました。参加者を15組に限定したこともあり、参加した方々同士の交流が生まれたことは嬉しかったですね。現在もリアルな場で人と会う機会が少ない状況は続いていますが、オンラインの企画の可能性を強く実感することができました。

村松勇輝(むらまつ・ゆうき)FICC メディア・プロモーション事業部京都 事業部長
村松勇輝(以下、村松):声を掛けていただいたのが2020年でしたね。うちの下の子が生まれた直後だったという、個人的なこともぴったりと合ったタイミングでした。本当に生まれたばかりの赤ちゃんを見ながら、STOKKEの仕事ができるのがすごく幸せなことだったんですよ。
いま改めて、STOKKEには僕自身も子育てについてだいぶ学ばせてもらっているな、と思いますね。上の子の時の子育てを思い返すと、もっと自分本位だったんです。なんで寝ないんだろうとか、早く泣きやんでほしいなと、どうしても親目線で思っていた。でも今すごく子ども目線になれているのは、この仕事をしているからではないか、と。
ちょうど昨晩も、怖い夢を見たのか子どもが夜中に急に泣き出して、全然泣き止まなかったんです。でも、イライラすることもなく、「きっと頭の中で処理できない何かが発生して、いま頑張って泣きながら整えてるんだろうな」と、思いやれるようになっていることに気づきました。子ども目線で考えていくーー製品作りにおいても、考え方すべてにおいて、親としてSTOKKEから学ばせていただいた実感があります。だから、本当に2年前と今の僕では、レベルが違うパパなんです。
福岡:それは素晴らしいですね。成長する親子!
村松:親が近くに存在するということを意識することが、子どもにとってどれだけいいことなのか、改めて気付かされたところがあって。そうだ、トリップ トラップのニューボーンセット、最高でした。

トリップ トラップの「ニューボーンセット」
福岡:生まれてすぐの赤ちゃんもテーブルを一緒に囲めるように「ニューボーンセット」ですね。STOKKEの人気製品です。日本では、離乳食が始まるあたりからテーブルで一緒にごはんを食べるようになりますが、ノルウェーでは、生まれたその日から家族団らんのテーブルで一緒にご飯を食べて、おしゃべりの輪の中にいるんです。そうやって新生児の時から家族の会話の中に入って、子どもは成長していくという考え方が根付いているんですね。これは、STOKKEがとても大事にしている考え方です。
村松:自分の人生と同じ目線で仕事ができるという、光栄な機会です。
福岡:FICCのプレゼンはすごい熱量でした。私と後藤は、感動で泣いてしまったほど。
後藤:共感しすぎてしまって(笑)。
村松:FICCチームには、学生時代に発達心理学を学んだ角屋(桃子)がいるので、プレゼンテーションでは「桃子の発達心理学メモ」というコーナーを設けるなど工夫もしましたね。
専門的な知識を企画に活かす
──発達心理学とはどんな学問なのでしょうか。

角屋桃子(かどや・ももこ)FICC メディア・プロモーション事業部京都 プロデューサー
角屋桃子(以下、角屋):とても簡潔に言うと、「人の一生における、心と身体の変化を研究する学問」です。私は教育の道に進もうかなと思っていた時期があって、子どもの心を理解できる教育者でありたいという思いから発達心理学を専攻しました。そこで学ぶうちに、日本には自己肯定感が低い子どもが多いということを知ったんです。そのことが自分の中で長く引っかかっていました。結局、教育の道には進みませんでしたが、STOKKEの企画を考えている際に、自己肯定感は、豊かな心を育み多様な社会を生きる力になり、自己肯定感を高めるためには人間関係や人格形成の出発点である、親と子の関係が大切だと学んだことを思い出しました。
STOKKEさんが大切にされている、親子の距離を縮めることで絆が深まり、子どもの自己肯定感につながるというコンセプトは、学問の中でも教育の中でも言われていることなので、それを体現して製品にしっかり取り入れているブランドがあるんだ!という、驚きと感動がありました。

福岡:そうだったんですね。
村松:計7人のチームで活動しているんですが、最終形の資料になる前段階で、アイデアや考え、学問的な知識をチームで出し合っていた時に、彼女(角屋)の想いが強く現れてきたんですよね。チームのリーダーとしても、僕はそういう想いは大切に伝えたいなと思いました。僕自身も父親ですし、チームにはあと3人パパがいるので、本当にみんなのいろいろな想いが詰まっています。
福岡:パパが育児に参加するということ、STOKKEの課題でもあるんです。FICCの皆さんは育児に積極的なイメージはありますけれど。
村松:そうですね。今はリモートで仕事できることもあるかもしれません。コロナの悪い面もありますが、前向きにとらえれば、家庭を見るきっかけができたのではないかと思います。
家族の在り方、父親の育児参加への課題を考える

福岡:STOKKEでももっと広めていきたいのが、北欧のライフスタイルです。ノルウェーでは、午後4時頃に仕事を終えて、保育園にお迎えに行って、家族そろって晩ごはんを食べるんです。家族の時間を本当に大事にするんですよね。女性も働いている人がほとんどですから、「専業主婦」という肩書きはないと言います。だからこそ、家族で過ごす夜の時間はとても大切にする。日本では、家族の時間にお父さんがいないことが多いじゃないですか。でも、村松さんがおっしゃっていたように、コロナ禍で家族と過ごす時間が増えて、これからもっと変わっていきそうな気配がありますよね。
村松:「孤独」の「孤」と書いて、「孤育て」。社会問題になっていますよね。まだまだニュースでも見かけます。
福岡:そうですね。私も2019年の8月に第1子を出産して、その後すぐにコロナの感染拡大が始まりました。だから、保育園に通わせて3年が経つのに、ママ友と交流する機会が全然ありません。保護者会やイベントもないですし。
──お母さんたちが交流をする場を作りたいという想いが、ストッケアカデミーに活かされているのでしょうか。

福岡:そうですね。FICCさんからご提案いただいたのも、完全にそこにフォーカスが当たっていました。ブランドを広めるということではなく、お母さん一人ひとりに寄り添った設計をする。だから、1回15人限定で、1ヶ月間、週に1度オンラインで参加してもらうことにしました。全4回のコースを完了すると、証書を発行して、第1期生、第2期生、第3期生……という形で開催しました。
参加してくださった方は妊娠中のお母さんが多かったので、途中で出産を挟んだ人もいて翌週には赤ちゃんと一緒に参加していることもありました。最終回にはオンライン交流会のような時間を設けたことや、SNS上で「#ストッケアカデミー」というハッシュタグを使って皆さんがつながれるようにしたこともあって、交流が生まれたんですよね。
みんな同じような悩みを持っていると聞いて安心したとか、プロの先生たちに答えてもらえる機会はありがたいというコメントも多く、嬉しかったですね。今後、そういうコミュニティをもっと作っていけたらいいなと考えているところです。
村松:それに、STOKKEを通じて友達ができたら自然とブランドのファンにもなってくれると思います。そういう世界をブランドとして作ることができるのがFICCの考えるブランドマーケティングの理想的だな、と。
後藤:生の声をたくさん聞けたことも嬉しかったですし、何より妊婦さん同士のつながりを作れたという実感もありますね。今も、参加された一人ひとりの顔が浮かぶほどです。1組15人という少ない人数でしたが、だからこそ、とても密でいい場になったのではないかな、と思ってます。
次なるプロジェクト「ストッケアカデミーmini」へつなぐ

──ストッケアカデミーは終了しましたが、今年は「ストッケアカデミーmini」が誕生しました。その経緯を教えてください。
村松:また違った形で継続して、プレママとプレパパに向けて何か役に立つことができないか、と。そのアイデアの一つがInstagramで発信する連載企画「ストッケアカデミーmini」でした。
福岡:もっと広く、多くの人に伝えていきたいと思ったんですよね。
──どのようにプロジェクトを進めているのでしょうか。
後藤:まずはFICCの角屋さんからいろいろなテーマをご提案いただいて、それに沿いながら、膨らませたら良さそうというコンテンツについてディスカッションしています。何もないところから、STOKKEがいま取り組んでいる内容に合う企画を考えてくれているのでありがたいですね。

角屋:アカデミーminiを通してSTOKKEが大事にしている「Here we grow」のメッセージがきちんと伝わるようになればいいなと思っていて。家族にとって心地の良い子育てのかたちを見つけてもらうためにも、子育てが楽しくなるヒントを発達心理学の側面から届けたいと考えています。後藤さんとは、子どもの成長に大切なことを話し合いながらすすめています。
後藤:私たち、本当にいろいろと語り合っていますよね(笑)。「今、こんな本を読んでいるよ」と、お互いに情報交換もしますし、子どもの心理や保育について、遊ぶ・学ぶとはどういうことだろう? 発達ってなんだろう? といったテーマは自分でも学びたいと思っていることなので、発達心理学の知識がある角屋さんと知り合うことができて嬉しいです。
ストッケアカデミーminiのために意見を交わすというよりは、子どもと成長していくことについて話し合ったということが、お互いの信頼関係を築くベースになっていると感じます。そうやってきちんと対話をしているので、アカデミーのためのテーマ設定も納得がいくんですよね。
福岡:私も、そうやって対話ができるのがFICCの特長という印象がありますね。クライアント側にいると、希望を伝えたら、「そうですか」とそのまま作ってくれるところはあるのですが、そうではなく、こんな方向性もいいのでは?とディスカッションがあるので、自分たちが予想していないほどいいコンテンツが生まれています。
──FICCにとって「対話」は、一つのキーワードに?

村松:そうですね。想いと想いが溶け合わさって価値に繋がっていくことを、FICC自体も大事にしてたりもするんです。ですから、そういう意味では、福岡さん・後藤さん個人としての想いも、直接お話しすることで伝わってきました。ブランドとしての想いもあるし、お二人ともお子さんがいらっしゃいますからお母さんとしての想いもあるし、女性、妻としての想い……全て受け止めて対話ができているのではないかと思います。こちらも、仕事を依頼されてる側という想いと、父親や夫としての想いもあわせて、対話をしながらやらせてもらえるのは貴重な機会ですね。
今後の展開について

──最後に、皆さんが子育てを通して感じていることと、今後のプロジェクトの展望を教えてください。
福岡:STOKKEでは、ノルウェーでの子育てについて本社のスタッフから学ぶんですよね。北欧では本当に夕方以降は仕事をしないんです。夏休みは1ヶ月取るし、その間はメールをしても何の音沙汰もありません。社会の制度が異なるからすぐに日本へ持ち込むというのは難しいかもしれませんが、北欧ではそんな暮らしが当たり前で、家族との時間や自分自身の時間をすごく大事にしているということをSTOKKEで働くなかでとても身近に感じるようになりました。
ちなみに私は昨年、地方へ移住したんです。子育ての環境を第一に考えて仕事をするという、心理的に大きな変化がありましたね。STOKKEではこれからも、オンラインでもリアルでもいいのですが、家族のためにいろいろなことを共有できる場づくりをしたいですね。
角屋:私は子育ての経験はないのですが、STOKKEから北欧の文化や子育て観について伺ったことで、また新たな視点が生まれました。文化の差があることを感じていますが、昔から私は「あらゆる文化や背景をもつ他者を理解できるような優しい子がこの社会に増えたらいいな」という想いが強かったことから発達心理学や教育について学んだ経緯があるので、これからも知識を活かしながらSTOKKEのお手伝いができたら嬉しいです。

村松:僕は子育てとSTOKKEの仕事を通してパパの存在意義について考えるようになりましたね。ママよりパパは子どもに懐かれにくい、とよく言うじゃないですか。まず大前提としてお母さんの中から生まれてきたので、赤ちゃんにとって一番の安全な場所がお母さんというのは当たり前だと思うんです。一方でお父さんの存在というのは、社会へつなぐ最初の役割を担えるんじゃないかなと。
そう思えるようになったのは、STOKKEの仕事を通して、本や先生から僕自身が学んだからなんですよね。子育てに対する意識がすごく変わったことを実感しています。学ぶことはやはり大事ですよね。知識があったら乗り越えられることが多くあるはずだから。世の中のパパやママに学びを提供することができたら、その先により良い子育てが広がっていくんだと思います。いつか、父親をサポートする施策もSTOKKEとできたらありがたいですね。
後藤:私は、社会に対していい影響があることをしたいという想いをずっと持っていて、そういう基準で仕事も選んできたところがあります。でも、私自身も子育てをするようになって改めて、いい世の中であってほしいと強く思うようになりましたね。子どもはもちろん守らなければならない存在ですが、自分とは違う人間だということも同時に考えます。自分で考えて判断して切り拓いていける人になるには、どれだけ私が何もしないかというのがすごく大事なのではないか、と。
ただ、社会に対して、理不尽だなと思うことや、どうしてサポートがないんだろう?と疑問に思うことがたくさんあるのは事実なので、子どもが大きくなった時にはきちんと整っていてほしいですよね。そんなことを通じて、自分ももう少し勉強しようと思うようになったんです。発達や子育て、保育について、世の中の仕組みについても。何をどう変えて、私たちにどんなことができるんだろう?と。社会のために、誰かのために……という意識が、子育てを通して本当に変わりましたね。
STOKKEは決して大規模な会社ではないのですが、だからこそ、直接的に誰かのために役立つことができた時、身近に感じることができます。もちろん最終的にビジネスにつながるのが一番ありがたいですが、目の前にいる人の明日がより良いものであってほしいと、本気で思える会社だと自負しています。FICCさん、今後ともよろしくお願いいたしますね!

FICCのメディア・プロモーション事業は、これからも社会問題に取り組むブランドのために、ブランドマーケティングの考えを通じて支援をしていきます。
執筆:中村志保 / 撮影:後藤真一郎
/assets/images/1827349/original/ba183d40-328f-4d0d-b610-99b6bf390a5e?1506933699)



/assets/images/1827349/original/ba183d40-328f-4d0d-b610-99b6bf390a5e?1506933699)


/assets/images/1827349/original/ba183d40-328f-4d0d-b610-99b6bf390a5e?1506933699)





/assets/images/13713877/original/ba183d40-328f-4d0d-b610-99b6bf390a5e?1687937910)
