目次
「八角形の物差し」への反旗——欠点こそが才能の源泉です
M&Aという葛藤の果てに掴んだ「経営者」としての覚悟
「父」と「母」が築く心理的安全性の土台——加山取締役との盟友関係
「愛と寛容」の本質——おっちょこちょいな仲間を救う再生の物語
ITは「武器」であり、凸凹な仲間を守るための「手段」です
究極のビジョン——「AK+の存在が必要なくなる社会」を目指しています
「これまでの常識の物差しで、あれこれと人が測られ、足りないところに目が行き、レッテルが張られる。そんな社会の不寛容さを、僕たちはITと愛、そして寛容さでぶち壊したいんです」。
株式会社AK+(エー・ケー・プラス)の代表取締役社長、浅岡浩平(あさおか こうへい)さんは、自らが策定した新ミッションの背景を語る際、静かな、しかし確かな熱を帯びた口調でそう切り出しました。2024年に情報戦略テクノロジー社(以下、IST)との資本提携を経て、同社は今、実質的な「第二創業期」の真っ只中にあります 。
浅岡さんが掲げる新ミッション「愛と寛容とITで、あらゆるすべてのポテンシャルを覚醒させる」という言葉は、単なる企業の目標ではありません。それは、彼自身の経営者としての葛藤と、AK+に集う「おっちょこちょいで不器用な」仲間たちが成し遂げてきた再生の物語が結晶化した、一つの哲学なのです。
「八角形の物差し」への反旗——欠点こそが才能の源泉です
AK+の哲学は、現代社会が当然のように受け入れている「評価基準」への強烈な違和感から出発しています。ミッションステートメントの冒頭で批判される「これまでの常識の物差し」とは、社会が個人を画一的に評価する際の基準を指しています。
「多くの企業や教育機関は、人の能力をレーダーチャートのような八角形で測ろうとしますよね。すべての項目で平均点、例えば7点や8点を取るような『丸い人材』を良しとして、わずかな『足りないところ』や『凹み』があれば、そこを突いてレッテルを貼ってしまう。でも、そんな画一的な物差しで人の価値が決まるはずがないんです」 。
浅岡さんは、自らの経営経験から導き出した独自の人間観を、実感を込めて語ります。
「僕たちが信じているのは、八角形のすべての項目が平均的な人ではありません。たとえ低いところが3点しかなくても、一つだけ突出し10点、15点というポテンシャルを持つ『凸凹(でこぼこ)』な人なんです。AK+に集まる社員は、大企業で働くエリートとは異なります。受験や就職活動で失敗したり、社会の枠組みからはみ出したりした経験を持つ『凸凹』な個性ばかりです。でも、その凸凹こそが、その人ならではの突出した強み(スペシャリテ)の源泉になると捉えています。『凸凹』な個性に光を当て、それを『才能』として覚醒させることこそが、僕たちの存在意義の根幹にあります」 。
M&Aという葛藤の果てに掴んだ「経営者」としての覚悟
しかし、この壮大なミッションに辿り着くまでの道程は、決して平坦ではありませんでした。特に2024年までのM&Aのプロセスは、浅岡さんにとって経営者としてのアイデンティティを問われる試練の連続だったといいます 。
「正直に言って、当初は売却に全く乗り気ではありませんでした。自分自身、経営者としては、組織の論理で社員の『尖った』個性を潰したり、首を切ったりするような窮屈な経営は絶対にしたくなかったからです。当時、AK+はSES事業で年商10億円という、僕個人の限界点に近い規模まで来ていましたが、それでも自分たちだけでやっていけると思っていました」。
その頑なだった浅岡さんの心を動かしたのは、新たなパートナーであるIST社の理念でした。そこには、浅岡さんが長年大切にしてきた「SEを大事にする」「多重構造をぶち壊す」といった考え方が、確かな意志として存在していたのです。
「IST社が、我々の理念と共通する部分を持っていることに気づいた瞬間、ふと視界が開けました。これまでは僕自身がトップセールスや営業責任者を兼任しながら走り続け、なんとか現場を回していましたが、それは組織としての成長を考えた本当の意味での経営ではなかったのかもしれません。自分の器が会社の限界になっていたんです。今こそ『真の社長』として組織をマネジメントし、社員の可能性を最大化するために舵を切る時だ。そう決断した瞬間に、M&Aは僕のモチベーションを爆発させる起爆剤になりました」。
浅岡さんは2025年2月14日の調印を終え、さらなる成長への旗手としての覚悟を固めました。
「父」と「母」が築く心理的安全性の土台——加山取締役との盟友関係
この変革期において、浅岡さんが「最高の壁打ち相手」と信頼を寄せるのが、創業時からの盟友である加山大介(かやま だいすけ)取締役です。二人の関係性は、AK+という組織の精神的な基盤そのものとなっています。
「加山は、僕が『社長をやる』と言ったときから、全力で賛成し、僕の考えが間違っているときは臆せず言ってくれる、最高の壁打ち相手です。僕がオペレーションや営業責任者という枠に留まらず、本当の意味での『経営者』として次のステージへ行くことを、誰よりも望んでくれました」。
一方、組織を裏側から支え続けてきた加山さんは、浅岡さんの変化をこう分析しています。
「ジョインしてからのこの1年弱、浅岡は本当に変わりました。以前の彼は、僕から見ても『オペレーションと営業が得意な人』に映っていたのですが、今や完全に『経営者』の顔つきになっています。彼が本気で社長業に突き抜けるなら、僕は全力でその土台を支えようと決断しました」。
この二人の経営スタイルは、組織において「父と母」のような役割分担として機能しています。浅岡さんが目標とビジョンを掲げ未来を指し示す「父」であれば、加山さんはすべてを受け入れ背中を押し続ける、慈愛に満ちた「母」の役割を担っています。
「愛と寛容」の本質——おっちょこちょいな仲間を救う再生の物語
AK+が掲げる「愛と寛容」という言葉は、同社が実際に社員に起こしてきた、リアルな「再生」の物語に基づいています。
「以前は、AとKで『熱い気持ち』という意味合いを大切にしてきましたが、経営陣で議論を重ねる中で、その二文字は『愛と寛容』であると定義し直しました。ここで言う愛とは、社員一人ひとりの個性や不器用ささえもすべて受け止め、その成長と幸せを願う、優しさと強さを兼ね備えた愛です。そして寛容とは、社会から『ポンコツ』や『不良』のレッテルを貼られた人たちをありのままで受け入れる広さのことです」。
その再生の象徴として語られるのが、現在、年商4億円規模のチームを率いるリーダーのエピソードです 。
「かつての彼は、税金未払いで銀行口座を差し押さえられるような、社会的な失敗を経験していました。でも、彼に変化をもたらしたのは、僕たちの指導というより、彼自身の『自覚』だったんです。才能や能力よりも、自分の弱いところも強いところも真摯に受け入れ、『変わろう』と素直に思えたとき、ポテンシャルは爆発的に覚醒します。自分の弱さを自覚しているからこそ、それを隠すのではなく、どう活かすかを考え、仲間に頼ることもできる。だからこそ、自らの弱さを自覚している人が活躍するチームは、強いんです」 。
ITは「武器」であり、凸凹な仲間を守るための「手段」です
AK+が事業としてIT、特にSES(システム・エンジニアリング・サービス)を選んでいる理由も、その根底には「仲間のための戦略」があります。
「僕たちにとってITは武器であり、手段なんです。たまたまITが成長産業で、安定的に稼ぐことができるから、不揃いな凸凹の仲間たちが安心・安全に成長し、活躍できる環境を維持するための『手段』として選びました。中でも経営が安定しやすいインフラ分野を主軸に置いているのは、デコボコな仲間たちを安定的に雇用し続けるための戦略的な選択です」。
その一方で、この「武器」は顧客の現場でも絶大な力を発揮します。
「凸凹な自分たちだからこそ、お客様の現場でも『すべてが整った状況ではなくても、なんとかしていきます』という強い決意を持って臨むことができます。それが現場やお客様、そして社会の可能性を広げることにつながる。私たちはITという武器を通じて、感謝と笑顔の連鎖を生み出していきたいんです」。
究極のビジョン——「AK+の存在が必要なくなる社会」を目指しています
浅岡さんが加山さんと共に描く未来の景色は、一企業としての存続を超えた壮大なものです 。浅岡さんは迷いのない視線で、最後にこう語りました。
「僕たちが目指すのは、世の中全体が『愛と寛容』に満たされることです。今はAK+という舞台が、社会の枠からはみ出した人たちの再生の場として必要かもしれません。でも、もし世界中が、ラベルに関係なく誰もが個性と能力を当たり前に発揮できる社会になったとしたら。そのとき、AK+という会社は存在意義を全うし、役割を終えます。『愛と寛容』の連鎖を、ポテンシャルの覚醒を信じるこの場所から、これからも広げていきます」。
AK+の「第二創業期」は、単なる企業の拡大ではありません。一人の経営者が掴んだ「愛」という名の決意が、社会の不寛容さを希望へと変えていく、壮大な挑戦の始まりなのです。






/assets/images/22548471/original/a190c83b-1fae-45c1-b656-d6ed395de3a8?1764039086)
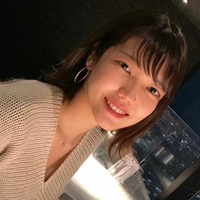
/assets/images/22548471/original/a190c83b-1fae-45c1-b656-d6ed395de3a8?1764039086)
